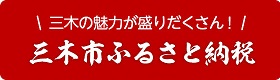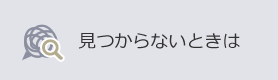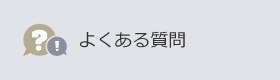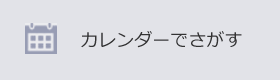後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度の概要
後期高齢者医療制度は、平成20年4月からスタートした高齢者の方の医療制度です。
制度の運営
都道府県単位で、すべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合<外部リンク>が制度を運営します。
三木市は、兵庫県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)に加入しています。
広域連合が保険料の決定や医療の給付を行い、三木市は被保険者証の引渡しや保険料の徴収などを行います。
被保険者(制度の対象者)
後期高齢者医療制度の被保険者となるのは次の方です。
- 75歳以上の人(全員加入)
- 65歳以上の人で一定の障害(※)があり、申請により広域連合の認定を受けた人(任意加入)
これまで国民健康保険などの医療保険の被保険者だった人はもちろん、会社の健康保険や共済組合等の被扶養者だった人も、それぞれの保険から脱退して後期高齢者医療制度の被保険者となります。
なお、生活保護受給中の方は対象外です。
1の方は75歳の誕生日から、2の方は広域連合の認定を受けた日から被保険者となります。
(※)一定の障害の認定基準
|
身体障害者手帳 |
1級、2級、3級 |
|---|---|
|
|
|
療育手帳 |
A判定 |
|
国民年金法による障害基礎年金 |
1級、2級 |
|
精神障害者保健福祉手帳 |
1級、2級 |
保険証
- 被保険者には、保険証(被保険者証)が一人に1枚交付されます。
- 75歳の誕生日を迎え、被保険者となるときは申請の必要はなく、誕生日までに保険証が交付されます。
- 医療機関等にかかるときは、必ず保険証を提示してください。
医療機関等の窓口での一部負担金
かかった医療費の1割、2割または3割を医療機関の窓口で負担します。
| 所得区区 |
一部負担金 |
判定基準 |
|---|---|---|
|
現役並み所得者 |
3割 |
同一世帯に、住民税課税所得額145万円以上の被保険者がいる方 ただし、以下のいずれかの条件にあてはまる場合は、1割または2割負担になります。 ○同一世帯に被保険者が1人の場合、収入額が383万円未満 ○同一世帯に70歳以上75歳未満の方がいる場合は、被保険者と70歳以上75歳未満 の方全員の収入合計額が520万未満 ○同一世帯に被保険者が2人以上の場合は収入合計が520万円未満 |
| 一般2 | 2割 | 以下の➀(2)の両方に該当する方 ➀同一世帯に住民税課税所得額が28万円以上145万円未満の被保険者がいる方 (2)「年金収入」+「その他の合計所得金額が 被保険者が1人・・・ 200万円以上 被保険者が2人以上・・・ 合計320万円以上 |
| 一般1・低所得 | 1割 | 同一世帯の被保険者全員が住民税課税所得額が28万円未満の場合、 または上記➀に該当するが(2)に該当しない方 |
療費負担のしくみ
医療費から窓口でお支払いいただく一部負担金を除いた給付費の約1割を皆さんからの保険料で賄います。
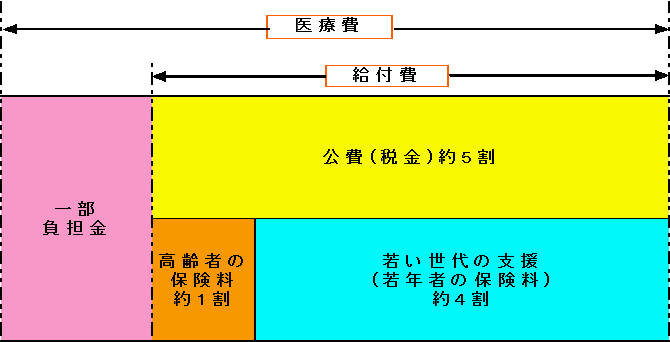
保険料
後期高齢者医療保険料は一人ひとり保険料を負担していただきます。
お支払いは原則、特別徴収(年金天引き)となっています。ただし、後期高齢者医療保険料と介護保険料を合わせた額が年金の2分の1を超える場合は年金からの天引きは行われません。
特別徴収(年金天引き)の方が、普通徴収(口座振替)への変更を希望される場合は申請してください。口座振替による支払いへ変更ができます。なお、申し出から特別徴収の中止までに数か月かかります。
配偶者など被保険者本人以外の口座からの支払いの場合、その社会保険料控除は、口座振替により支払った方の対象となり、世帯全体の所得税および市民税が減額となる場合があります。
※保険料の滞納が見込まれる場合には、口座振替への変更が認められないことがあります。
保険料の決まり方
年間の保険料は、皆さんが等しく負担する「均等割額」(定額)と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。
| (1)均等割額 | 50,147円 |
|---|---|
| (2)所得割額 | (総所得金額等-基礎控除43万円)×所得割率10.28% |
| (3)保険料額(年間)(1)+(2) | 上限66万円 |
※均等割額と所得割率は、2年ごとに見直され、兵庫県内で原則均一となります。
※総所得金額等=収入額―控除額(公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費)
※合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その金額に応じて段階的に基礎控除額が減少します。
所得の低い方の軽減
均等割額の軽減(令和5年度)
同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が、次の基準額以下の場合、均等割額が軽減されます。
| 所得金額等(被保険者+世帯主)が次の基準以下の世帯 | 軽減割合(軽減後の均等割額) |
|---|---|
| 43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1) | 7割(15,044円) |
| 43万円+29万円×被保険者の数+10万円×(年金・給与所得者数-1) | 5割(25,073円) |
| 43万円+53.5万円×被保険者の数+10万円×(年金・給与所得者数-1) | 2割(40,117円) |
被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に会社の健康保険等の被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額は賦課されず、資格取得後2年を経過する月までの間に限り均等割額が5割軽減されます。
保険料の減免
災害で大きな損害を受けたとき、所得の著しい減少があったときなど、申請により保険料の減免を受けることができる場合があります。