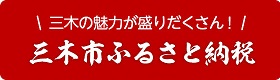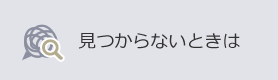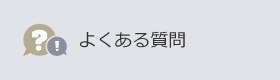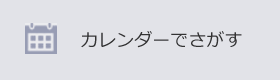地震による電気火災対策を!
感震ブレーカーが効果的です!
「感震ブレーカー」をご存知ですか?
地震がおさまって電気が復旧した際に、倒れた電気製品や破損した電源コード等が火元となり発生する「通電火災」。多くの方の記憶に新しい東日本大震災では、火災発生原因のうち原因が特定できた54%が電気関係の火災だったといわれており、また、都心南部直下地震時の火災による被害は、41万棟・死者1万6千人に達すると想定されています。
そのためこれからの住まいには、この「通電火災」への対策が必要となり、「感震ブレーカー」はそうした二次災害に備える役割があります。
●内閣府の首都直下地震対策検討ワーキンググループでは電気関係の出火防止対策として、感震ブレーカーなどの設置を進めることにより、火災による建物消失などが約5割減少すると予測しています。

感震ブレーカー等のタイプ別の特徴 [PDFファイル/524KB]
通電火災の対策について
通電火災とは
停電が発生し、その後電気が復旧した際、可燃物が落下した電気ストーブや破損した電源コードなどに再び電気が通ることが原因で起きる現象をいいます。
通電火災を防ぐためには
1.停電中は、電気機器のスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。
2.停電中に自宅から離れる際は、ブレーカーを落とす。
※行政から避難指示等が発令され、自宅から避難する場合は特に心掛けてください。
上記「通電火災を防ぐためには」のように、電気の電源を遮断することが効果的です。しかし、避難時等の緊急性が高い時、または外出中は電気を遮断することができません。そこで、地震発生時には電気を自動で遮断してくれる「感震ブレーカー」が効果的です。
ただし、自分の家だけ感震ブレーカーを設置して火災を防いでも周囲からの火災は防ぐことはできません。地域一帯で設置することで、その効果は一層期待されるものです。今一度隣近所の方と地震対策や感震ブレーカーの有用性について話し合う機会を設けましょう。