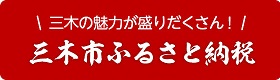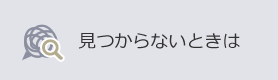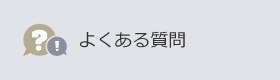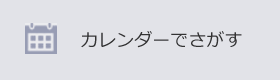令和7年度9月分 学校給食献立の紹介
9月分 学校給食献立の紹介
9月は残暑が厳しいため、ガーリックパウダーやカレー粉で香りを付けたり、煮物を避けるなどして、できるだけ食べやすいメニューにしました。旬の食材としてなす・ピーマン・さんま・ぶどうを取り入れます。
| Aコース:9月2日(火曜日) | Aコース:9月3日(水曜日) |
| Bコース:9月3日(水曜日) | Bコース:9月2日(火曜日) |
 |
 |
|
主食:コッペパン 主菜:煮込みハンバーグ 副菜:コーンと人参のコンソメ煮 汁物:冬瓜のスープ 飲み物:牛乳 |
主食:ごはん 主菜:マーボー豆腐 副菜:シラスと野菜の炒め物 飲み物:牛乳 その他:オレンジゼリー |
| 市内産:玉ねぎ | 市内産:米 |
|
冬瓜のスープを食べている子どもに「どうして冬の瓜と書くのに夏に食べるの?」と質問されました。冬瓜は夏野菜ですが、冬まで保存することができるので『冬瓜』と書きます。食べ物には漢字を知るとおもしろい発見があることもあるので、漢字の書き方も調べてみてください。また、冬瓜には水分が多く夏バテを防ぐ効果があります。 |
9月に入りましたが、まだまだ暑い日が続きますね。食欲が増すよう、トウバンジャンを使ったマーボー豆腐と少しでも暑さが吹き飛ぶようにと冷たいオレンジゼリーを提供しました。 |
| Aコース:9月4日(木曜日) | Aコース:9月5日(金曜日) |
| Bコース:9月5日(金曜日) | Bコース:9月4日(木曜日) |
 |
 |
|
主食:コッペパン 主菜:ツナじゃが 副菜:切干し大根のソース炒め 飲み物:牛乳 |
主食:わかめごはん 主菜:鰆のごま香味焼き 副菜:煮豆 汁物:大根の味噌汁 飲み物:牛乳 |
| 市内産:玉ねぎ・じゃが芋・もやし | 市内産:米・玉ねぎ・青ねぎ |
|
切干し大根のソース炒めは、給食のような大量調理では難しい焼きそばをイメージした一品です。切干し大根のソース炒めをパンに挟んで焼きそばパンのように食べる子どももいて、子どもたちにも人気です。切干し大根は、大根を干して作られた保存食で、カルシウムや食物繊維が豊富です。歯ごたえがあり、よく噛むことで満足感もアップします。 |
煮豆は、大豆・人参・こんにゃくを、砂糖・醤油・みりん・かつおだしで甘く仕上げました。子どもたちも、「甘くておいしい」とたくさん食べており、ごはんの進むメニューでした。 |
| Aコース:9月8日(月曜日) | Aコース:9月9日(火曜日) |
| Bコース:9月8日(月曜日) | Bコース:9月10日(水曜日) |
 |
 |
|
主食:ごはん 主菜:豚じゃがキムチ 副菜:クイッティオのサラダ 飲み物:牛乳 |
主食:コッペパン 主菜:鮭ボールのフライ 汁物:春雨の坦々スープ 飲み物:飲むヨーグルト(ブルーベリー) |
| 市内産:米・玉ねぎ・じゃが芋 | 市内産:玉ねぎ・じゃが芋・もやし |
|
豚じゃがキムチは、韓国の代表的な食材「キムチ」と、日本の家庭料理「肉じゃが」を組み合わせた、うま味たっぷりのメニューです。豚肉にはたんぱく質やビタミンB群が豊富で、疲れにくい体づくりを助けてくれます。キムチには乳酸菌が含まれていて、おなかの調子を整える働きがあります。ピリッとした辛さが食欲をそそり、ごはんが進む一品です。 |
新メニューの春雨の坦々スープです。最初に豚ひき肉をしっかりと炒めてガーリックパウダーで香りを付けました。野菜と春雨を煮込んだら豆乳を加え、味噌・チキンスープ・みりん・少量の豆板醤で味を整えました。春雨は、じゃがいもや緑豆などから作られる、つるつるとした食感が楽しい麺です。これからもおいしい給食を提供できるように新メニューの開発に取り組むので、楽しみにしていてください。 |
| Aコース:9月10日(水曜日) | Aコース:9月11日(木曜日) |
| Bコース:9月9日(火曜日) | Bコース:9月12日(金曜日) |
 |
 |
|
主食:ごはん 主菜:鯖の塩焼き 副菜:ピーマンのおかか和え 汁物:玉ねぎの味噌汁 飲み物:牛乳 |
主食:黒糖パン 主菜:オムレツ 副菜:野菜のケチャップソテー 汁物:かぼちゃのコンソメスープ 飲み物:牛乳 |
| 市内産:米・玉ねぎ・じゃが芋・ピーマン | 市内産:玉ねぎ・マッシュルーム・かぼちゃ |
|
ピーマンは、6月~9月が旬の夏野菜です。夏の日差しをたっぷり浴びて育ったピーマンは、香りも味わいも豊かになります。栄養価が高く、特にビタミンCが多く含まれており、疲労回復の効果があります。栄養たっぷりの夏野菜をたくさん食べて、夏の疲れを吹き飛ばしましょう。 |
かぼちゃの旬は秋です。日本では、だいたい9月~11月にかけて収穫されることが多く、甘みが増して美味しくなる時期です。ただし、かぼちゃは保存性が高いため、収穫後しばらく寝かせてから出荷されることもあり、冬至に食べる習慣もあります。ビタミンAが豊富で、目や肌の健康を守ってくれる野菜です。コンソメスープにすることで、やさしい味わいになり、かぼちゃの甘みが引き立ちます。 |
| Aコース:9月12日(金曜日) | Aコース:9月16日(火曜日) |
| Bコース:9月11日(木曜日) | Bコース:9月17日(水曜日) |
 |
 |
|
主食+主菜:夏野菜カレー(麦ごはん) 飲み物:牛乳 その他:ぶどう |
主食:ごはん 主菜:鶏肉のガーリック焼き 副菜:人参しりしり 汁物:みぞれ汁 飲み物:牛乳 |
| 市内産:米・玉ねぎ・じゃが芋・かぼちゃ・なす・ぶどう | 市内産:米・青ねぎ |
|
三木市内で作られたぶどうを提供しました。ぶどうは三木市特産品です。つぶれてしまわないよう、調理場では慎重に房からはずし、消毒した後何度も洗い、クラスごとに分けました。これからも三木市の特産品を知り、食べ、大切に思う気持ちを持ってほしいです。 |
みぞれ汁は新メニューです。かつおと昆布で出汁をとったお吸い物に大根おろしを加えた汁物です。すりおろした大根が雪のように見えることから「みぞれ」と呼ばれています。大根には、消化を助ける酵素が含まれていて、胃腸の調子を整えてくれる働きがあります。具だくさんの汁物はこの時期食べにくいのですが、しっかりと野菜を食べてほしいという願いを込めています。 |
| Aコース:9月17日(水曜日) | Aコース:9月18日(木曜日) |
| Bコース:9月16日(火曜日) | Bコース:9月19日(金曜日) |
 |
 |
|
主食:ごはん 主菜:マーボーなす 汁物:トックスープ 飲み物:牛乳 |
主食:コッペパン 主菜:ひじきとツナのスパゲッティ 汁物:かぼちゃの豆乳スープ 飲み物:牛乳 |
| 市内産:米・なす・玉ねぎ・青ねぎ | 市内産:玉ねぎ・かぼちゃ |
|
トックは、韓国語で「餅」のことです。日本の餅の原料は「もち米」ですが、トックの原料は「うるち米」です。トックスープは、韓国ではお正月に食べる風習があります。白色は『純粋』や『始まり』を象徴するといわれ、韓国の旧正月にはトックスープが各家庭で食べられます。 |
ひじきとツナのスパゲッティのひじきは、カルシウムや鉄分、食物繊維が豊富な海藻で、昔から日本の食卓で親しまれてきた健康食材です。ツナには良質なたんぱく質とDHAが含まれていて、脳の働きを助ける栄養素としても注目されています。和の食材を洋風のスパゲッティに合わせることで、食べやすく、栄養もたっぷりの一品になっています。 |
| Aコース:9月19日(金曜日) | Aコース:9月22日(月曜日) |
| Bコース:9月18日(木曜日) | Bコース:9月22日(月曜日) |
 |
 |
|
主食:ごはん 主菜:鰹と大豆のごまがらめ 汁物:じゃが芋の味噌汁 飲み物:牛乳 |
主食+主菜:焼き飯風混ぜごはん 汁物:卵入りサンラータン 飲み物:牛乳 |
| 市内産:米・じゃが芋・玉ねぎ | 市内産:米・卵・ピーマン・玉ねぎ |
|
鰹は旬が2回ある魚です。4~6月が旬の初鰹は、脂が少なく身が引き締まっていて、さっぱりとした味わいです。9~11月が旬の戻り鰹は、脂が多く濃厚な味わいです。鰹は良質なたんぱく質が含まれており、筋肉の成長を助けてくれます。旬による味などの違いを、ぜひ味わってみてください。 |
市内産の卵を使ったメニューです。サンラータンとは漢字で書くと「酸辣湯」と書き、「酸=すっぱい」「辣=辛い」「湯=スープ」であり、本来、辛みと酸味を効かせたスープですが、給食では幼稚園の子でも食べられるようマイルドな味付けにしています。酢に含まれる「クエン酸」の疲労回復効果でこの暑さも乗り越えてほしいと思います。 |
| Aコース:9月24日(水曜日) | Aコース:9月25日(木曜日) |
| Bコース:9月24日(水曜日) | Bコース:9月26日(金曜日) |
 |
 |
|
主食:ごはん 主菜:秋刀魚の竜田揚げ 副菜:小松菜のごま和え 汁物:さつま芋の味噌汁 飲み物:牛乳 |
主食:コッペパン 主菜:クリームシチュー 副菜:カリカリじゃこサラダ 飲み物:牛乳 |
| 市内産:米・さつま芋・玉ねぎ・もやし・青ねぎ | 市内産:じゃが芋・玉ねぎ・もやし |
|
今日の給食で秋が旬の食材は、秋刀魚とさつま芋です。秋刀魚は9~10月が旬で、「秋刀魚」と書くように秋の代表的な魚です。さつま芋は10月~1月が旬ですが、収穫時期は8月~11月ごろです。収穫した後に少し寝かせることで、より甘みが増します。このように、給食には旬の食材をたくさん使用します。旬の食材や良さを知って、これからもたくさん食べてほしいと思います。 |
カリカリに炒めたちりめんじゃこをのせたサラダは、食感が楽しく、カルシウムもしっかりとれるメニューです。野菜と一緒に食べることで、ビタミンや食物繊維もとれ、体の調子を整えてくれます。また、よく噛んで食べることで、満足感もアップします。9月の給食だよりにもカリカリじゃこサラダのレシピを載せているので、ぜひご家庭でも作ってみてください。
|
| Aコース:9月26日(金曜日) | Aコース:9月29日(月曜日) |
| Bコース:9月25日(木曜日) | Bコース:9月29日(月曜日) |
 |
 |
|
主食:ごはん 主菜:醬油ラーメン 副菜:五目野菜炒め 飲み物:牛乳 その他:のり佃煮 |
主食:ごはん 主菜:シイラの煮つけ 副菜:こんにゃくと大豆の炒り煮 汁物:野菜雑煮 飲み物:牛乳 |
| 市内産:米・ピーマン・青ねぎ | 市内産:米・青ねぎ |
|
昨年に引き続き、今年もラーメンを提供しました。ラーメンのスープと麺は、それぞれで調理・配食し、各クラスで盛り付けるときにスープの中に麺を入れて食べました。スープの味もしっかりしており、麺も伸びすぎず程よい柔らかさだったので、大人も子どもも「おいしい」とたくさん食べてくれました。 |
シイラは給食でよく食べますが、スーパーや飲食店で見かける機会が少ない魚です。英語ではドルフィンフィッシュ、ハワイ語ではマヒマヒと呼ばれ、様々な国で食べられている高級魚です。日本では6月~10月の暖かい時期の黒潮にのってやってきて、鹿児島から新潟にかけての対馬海州域、黒潮域の高知県でとれます。シイラの身は柔らかく、しっとりした食感で脂が少なくクセがないので焼き物、揚げ物、今日のような煮物でも美味しく食べられます。 |
| Aコース:9月30日(火曜日) | |
| Bコース:9月30日(火曜日) | |
 |
|
|
主食:ごはん 主菜:鶏とレバーのカレー和え 汁物:レタスと白いんげん豆のスープ 飲み物:牛乳 |
|
| 市内産:米・玉ねぎ・青ねぎ | |
|
白いんげん豆とは、いんげん豆の仲間で白色の豆のことです。味は淡白で、茹でるとほくほくとした食感になるのが特徴のため、スープや煮込み料理に入れるのがおすすめです。今日は、スープに入れて提供しました。白いんげん豆には、血圧を下げてくれるカリウムやマグネシウム、便秘を予防してくれる食物繊維など、様々な栄養素がたくさん含まれています。 |