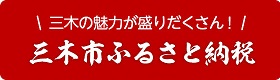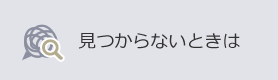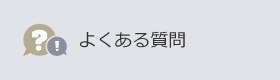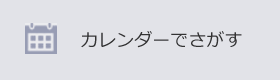三木金物
三木金物について

三木金物製品の特徴は伝統に培われた優れた技術を生かした品質、性能の高さであり、全国的に高く評価されています。なお、”三木金物”は特許庁の地域団体商標として登録を受けています。
三木金物ホームページ(日本語)<外部リンク>
Miki hardware website(English)<外部リンク>
歴史

三木市が全国屈指の金物のまちとして栄えるきっかけとなったのは、天正六年(1578年)、羽柴秀吉の三木城攻めでした。秀吉の兵糧攻めに敗れた三木城主別所長治は自刃しました。
秀吉は焼け野原となった三木の町の復興を考え、免税政策をとって四方に散らばった人びとの呼び戻しを図りました。復興のために集まった大工職人、その道具を作る鍛冶職人が次第に増え、三木の町も活気づいていきました。
復興が一段落すると、大工の仕事がなくなり、大工職人たちはやむなく京都、大阪などへ出稼ぎに行くようになりました。そのときに大工が持参した道具の素晴らしさが評判になり、鍛冶の里三木としての地盤を固めていきました。
そして現在に至るまで、伝統の技を基礎として多くの優れた金物が開発・生産され続けています。
伝統的工芸品「播州三木打刃物」

三木金物製品のうち、鋸(のこぎり)、鑿(のみ)、鉋(かんな)、鏝(こて)、小刀(こがたな)の5品目が国の伝統的工芸品に指定されています。
伝統的工芸品とは(経済産業省ホームページ)<外部リンク>
播州三木打刃物について(伝統工芸青山スクエアホームページ)<外部リンク>
金物鷲
金物鷲は、鋸(のこぎり)や包丁(ほうちょう)、ナイフ、ギムネ、鉈(なた)、手鈎(てかぎ)など総数にして約3,300点の三木金物製品を組み上げた大きな鷲のオブジェです。重さ1.5トン、翼長5m、高さ3.2mの威容は、多くのイベントに出展され、三木金物のシンボルとして注目されています。
よくある質問
Q:「三木金物」にはどんなものがありますか?
鋸(のこぎり)、鏝(こて)、鑿(のみ)、作業工具(バール、クランプなど)、鎌(かま)、鍛工品(たんこうひん)、鉋(かんな)、機械工具(ドリル・ホールソー)、ナイフ・小刀(こがたな)などです。この他にも様々な種類の金物が生産されています。
Q:三木金物はどこで手に入りますか?
三木金物は、国道175号沿いにある「道の駅みき」2階の『金物展示館』(三木市福井2426番地先 Tel:0794-82-7050)などで販売しています。日曜大工、園芸、料理などにお使いいただき、三木金物の良さをぜひ体感してください。
Q:三木市では三木金物に関してどのような施策を行っていますか?
三木市では三木金物業界関係団体の皆様と連携を図り、次のような施策を行っています。
- 三木金物ニューハードウェア賞製品を募集、認定し、全国へ情報発信するとともに、開発事業所へ助成を行うなど、新製品の開発を支援しています。
- 全国の三木金物取扱小売店の方に実際に三木金物製品に触れ、三木金物の良さを知っていただき、販売の促進につなげていただくため、三木金物大学を開催しています。
- JAPAN DIY HOMECENTER SHOW、東京インターナショナル・ギフト・ショーなど各種見本市へ積極的に出展する事業所へ助成を行い販路開拓を支援しています。
- 三木金物まつりやJAPAN DIY HOMECENTER SHOWなどの見本市に金物鷲を出展し、三木金物を情報発信しています。
- 伝統ある三木金物の製造技術を伝承する後継者を育成するため、伝統工芸士等の後継者育成に対して支援を行います。