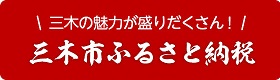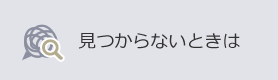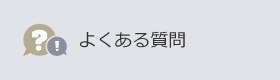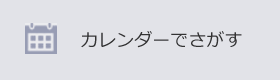大宮八幡宮例大祭宮入宮出の屋台練り(市指定文化財)
大宮八幡宮例大祭宮入宮出の屋台練り (おおみやはちまんぐうれいたいさいみやいりみやでのやたいねり)
| 指定区分 | 市指定文化財 |
| 種 別 | 無形民俗 |
| 指定年月日 | 平成21年9月16日 |
| 年 代 | 江戸時代 |
| 所有者 |
大宮八幡宮秋祭り大当番 |
| 所在地 | 本町2丁目19-1 |
| 概 要 | |
|
屋台の宮入は、担ぎ手に担がれた氏子各町の屋台が、約16mの高位にある境内までの約21度余りの傾斜をもつ85段の石段を上っていく練りで、宮出は、屋台を担ぎ同じ石段を下がっていく練りをいう。 祭礼における屋台がいつ頃から出現するのか定かではないが、「前田町記録帳・御林山覚」の「九月十三日祭礼神事檀鶴(だんづる)ノ訳」に「享保年中檀鶴毎年有之所 其後三十年中絶 又々宝暦元年ニ初ル」とある。この「檀鶴」がどのような形状をしていたのか不明であるが、享保年間には屋台の原型と考えられる練り物が繰り出されていたことをうかがわせる。 このような屋台を担ぎ、石段を上り下りする宮入宮出の練りは、播州地方でも見られない独特な練りである。 |
|